新卒で一部上場企業に入社の末、2年半で退社したのですが、それ以降は零細企業2社に勤めました。
一つは稲作中心の農業法人であり、もう一つは食品製造販売の会社です。
いずれも従業員数10名程度の会社です。
今になって思えば、新卒で入社した会社がそれなりの大企業であり、隅々までしっかりとしていると思えます。
それほどに地方の零細企業は適当であり、何から何まで雑です。
同じ会社かと思えるくらい。
例えば、整理整頓の仕方一つにしても、片や全てマニュアル化されており、一方では各従業員の判断による。
従って、零細企業においては、片付けが下手な人が揃ってしまえば永遠に整理整頓がされないままにもなりかねないということです。
本当です。
私は、皮肉ではなく本当に、新卒でそれなりの大企業と呼ばれるところに入社して「これが会社であり、マネジメントである」という見本のような場所で働くことができて良かったと思っています。
片付けがそれほど上手ではない私ですが、整理整頓の基礎を働きながら学ぶことができ、それは以降の零細企業においてかなり生かされています。
マネジメントの基礎のようなものも習得できています。
そんな私から見た零細企業のブラックさは大きく3点に絞られます。
私は決して大企業を持て囃したいわけではありませんし、自慢したいわけでもありません。
ただ、あまりにも多くの地方零細企業は何も考えてなさすぎじゃないかと思ったので、こうして考えを整理していこうと思うのです。
1. ワンマン経営 ―行動力だけはやたらある社長
問題点は全てここに集約されていると言っても過言ではありません。
ワンマン経営です。
国の運営でさえ三権分立がメジャーであるにも関わらず、零細企業においては全てが社長と呼ばれる人物の手に掌握されています。
社長というと「すごい人」と思うかもしれません。
実は、そんなことはありません。
社長は「行動力」さえあれば誰でもなれます。
そして、社長と呼ばれる人物の99%は「行動力しかない」のではないかと思っています。
社長の謎の行動力によって迷惑を被るのは従業員です。
「明日の朝までにあれを作っておいてくれ」と思い付きで指示を出します。
「ごめん、今日なんだけどさ出張行ってくれる? 俺、孫の運動会に行かなきゃ行けないんだよね」と当日の朝、指示されます。
全てが思い付きで発動される傾向にあります。
そんな社長を注意する人は、当たり前ですが誰もいません。
人事権も社長が掌握しているのでやりたい放題です。
新しく入社してきた人をしばらくは重宝して、少しでも悪い部分が見えてきたり飽きてきたりすると左遷するのは常套手段。
入社時に口約束で決めた基本給を勝手に下げる(入社直後、「子供が熱を出した」と急に休んだ腹いせ)。
気に入らない者がいればこれも思い付きで強引な人事を行う。
と思えば、自分に都合の悪いことは先延ばしにして全くやらない。
そんな社長を叱咤する人は、当たり前ですが誰もいません。
全ての社長に経営の資質があるというのも間違いです。
少なくとも、私が入社した2社の社長は経営力によって会社を運営しているというよりは、その場その場の謎の行動力によって自転車を倒れないように漕いでいる経営スタイルでした。
長期的視点は皆無で、繰り返すようですが、全てがその場の思い付きです。
2. 逃れられない濃密な人間関係 ―異動の必要性
大企業のごちゃごちゃした人間関係にやや疲れていた私は、従業員10名ほどの農業法人に就職が決まり、「ここなら複雑な人間関係はなさそうだ」と溜飲が下がりました。
そんなことはありませんでした。人間関係の問題のない組織は存在しない。
その会社は「生産部門」と「管理部門」とに分かれていて、私は管理部門に在籍していたのですが、どうやら両者の仲はかなり悪いらしくそれに私も入社早々巻き込まれつつあったのでした。
ああ、面倒くさい。
従業員の少ない零細企業と言えども、人間関係の問題がないなんてことは絶対にありません。
これから就職しようとしている人の中に、もしかしたら「少人数で和気あいあいと家族みたいな仲良しな会社っぽいな」と勘違いをして零細企業に希望を持って入社しようとしている人がいたら、それは間違いであると思ったほうがよいでしょう。
「人間関係」以外の基準で入社を決めて下さい。
遅かれ早かれ、何らかの問題は発生します。
永遠に皆が仲の良い組織は存在しないと考えましょう。
そう考えると、私が新卒で入社したスーパーマーケットもそうでしたが、異動が多いということも人間関係をリセットできるというメリットがあったのだなと思うわけです。
嫌な上司の下で働かなくてはならなくなったとしても、それは長くは続かない。
自分か上司が異動してしまえば解決するわけです。
それに対して零細企業では、人間関係は永遠にそのままです。
一旦誰かと険悪になってしまうと、どちらかが辞めるまでその問題は継続されてしまいます。
小規模の濃密な逃れられない人間関係がそこにはあります。
3. ルールがない ―カオス状態
一流企業とそれ以外の企業の決定的な違いは、ルールやマニュアルが明確であるかそうでないかであると私は考えています。
一流企業においては接客もマニュアル化されているので、クレームが少なく自社の目指す気持ちのよい接客を誰もが習得できるようになっています。
一方、マニュアルのない零細企業においては、それぞれのやり方でやることになるためトラブルになりやすい。
そのトラブルというのは、お客さんとのトラブルもそうですが、従業員同士のトラブルも含みます。
ルールやマニュアルがないために従業員それぞれのやり方でやらざるを得なく、ある人のやり方が気に入らないという人が出てきても明確な基準による対処のしようがないわけです。
例えば、「私は、お札を先に渡して小銭は後から渡したほうがお客さんのためだと思う」という人もいれば、「お札も小銭もレシートも同時に渡したほうが効率的だ」という人もいるわけで、双方の主張がぶつかりあった場合大きなトラブルになりかねないということです。
「なにをそんな細かいことを」と思うかもしれませんが、人間関係のトラブルは常にこういった細かいところから発生するものです。
そして、その細かいトラブルは、もしかしたらマニュアルやルールがしっかりとしていれば未然に防ぐ事ができたことかもしれないのです。
先程、「社長は行動力だけはやたらある」と書きましたが、私の観察によれば、行動力のある人物はルールを守らない。
つまりは、零細企業における問題点として、「ルールがあったとしてもそれを社長自身が破ってしまう」ということが挙げられます。
そうなれば、社長への不満は募り、社長が懇意にしている従業員への不満も同時に募り、そのルールが従業員間でも無視されることによってさらなる従業員同士の軋轢を生むということになりかねないわけです。
労働条件に関する規定・ルールも曖昧な場合が多く、そうなると長い時間働いている者や自発的に動いて生産性の高い仕事をする者は、定時で帰る者やだらだらと仕事をする者に不満を募らせることになるわけです。
で、「あまりにも仕事をしない人がいるので何とかして欲しい」と生産性の高いきちんとした人が社長に要望したところ、なぜか社長は面倒くさがって、その生産性の高いきちんとした仕事をする人を「ごちゃごちゃうるさい」という理由で解雇してしまいました。意味不明。
それでも、そんな社長を諌める人は誰もいません。
まとめ:ちょっと不安な零細企業
経営者への不満みたいなものが大半を占めることになってしまい、とりとめもないのですが、全て私が実際に体験・見聞きしたものです。
要は、「経営者に経営の資質がない」という結論に集約されるところです。
全ての零細企業がこうであるとは言いませんが、少なくとも全ての会社社長がきちんとした長期的視点で経営をしているとは限りません。
就職活動・転職活動をしている人においても、地方の従業員10名程度の会社に応募しようと思う、あるいは内定が出てしまったという人がいるかと思います。
零細企業には、「給与が低い・退職金がない・賞与(ボーナス)がない」以外にも実際にその会社で働いてみないとわからないメリット・デメリットがあります。
私は上記でデメリットばかり挙げてしまいましたが、メリットも少なからずあります。
例えば、ルールがきちんとしていないということは、融通が利くということでもあります。
私はそれを利用して、勝手に1週間の休みを取得して北海道旅行に行ったり、なんか疲れたなと思ったらシフトを週3出勤にして家で休んだりしています。
とは言え、零細企業は所詮零細企業。
トップの独りよがりな経営によっていつ倒産するかわからないし、この給与ですから、この先が大変に不安であるのが実情です。
小さな会社の社員でもフリーターでも、生きていくことだけならできる。だけど、不安は常にのしかかる。
そう考えると、就活生の大企業志向も強ち間違いではないなと思うのでした。
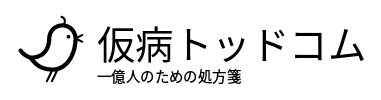

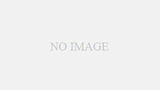
コメント