我々の仕事の期限は定時である。5時である。
間違っても終電ではない。
これは勘違いされやすいことなので、まずは覚えておこう。
「終電までに退勤すればいいや」と思っていた人は、それが間違いであると気づくことから全ては始まる。
基準は、定時である。5時である。
大事なことなので何度でも繰り返す。
定時に帰ること。
そう、社会人たる我々は定時に帰るために仕事をしているのである。
現在では各企業におけるコンプライアンスが滅茶苦茶なので、残業代が出なかったりするわけだが、「残業代が出ないということは終電まで働いていい」ということにはならない。
残業代の割増賃金が一円たりとも支給されないのであれば、むしろ、定時で帰るべきである。
百歩譲って残業代が出るのであれば、たまには残業してやってもいいが、残業代が出ないのに残業することほど馬鹿げたことはない。
そのことに気づくべきである。
自分はさっさと定時で帰りたいのに上司が帰らせてくれないのなら、「残業代が出ないのに残業することほど馬鹿げたことはない」と上司のデスクに彫刻してやってもいいくらいなものだ。
定時で帰ろう。
さっさと帰宅して人生を楽しもう。
ここに紹介するのは定時で退勤するための仕事術7選であり、間違っても仕事をバリバリこなして昇進するためのものではない。
1. 仕事を邪魔されないで集中するための3つの方法
効率的な仕事は集中力にかかっている。
誰もが集中して仕事をすれば定時に退勤できる可能性を秘めているにも関わらず、だらっとして終電を迎える。
集中することによって人生が変わる。何でもできるようになる。
何事にも中途半端だった人生とはさよならだ。
1-1. 「2分ルール」を実行する
生産性の世界的権威デビッド・アレンは「2分でできると思うことは今すぐにやってしまおう」と提案している。
それが「2分ルール」である。
単純なことと思うだろうけれど、効果は絶大である。今からでも試しにやってみて、是非とも習慣にしよう。
2分ルールの積み重ねによって、「一日に1時間も自由な時間ができた」という報告もある。
もちろん、仕事だけではなく、家での家事や片付けにも役立つ考え方である。
1-2. 集中していることを周囲に示す
「集中したいから話しかけないでくれ」と周囲に時間を指定して釘を差しておくのでもいいし、わざわざヘッドホンをして仕事をするのでもいい。
何でもいい。アイデアは無限大だ。
これによって、第三者から邪魔をされずに済むのである。
仕事が妨害される一因に、「どうでもいいことに対応しなくてはならずに手が止まる」というストレスフルな事象があるが、誰かがあなたに話しかけたり頼ったりしなくても、殆どの場合、職場の仕事は円滑に進むのである。
あなたはあなたの集中すべきことに取り組んでいればいいのである。
1-3. 集中できるように自分の環境を見直す
実は、集中力を邪魔する最大の要因は、他でもない自分なのである。これは本当の話。
他人に妨害されるよりも、自分で勝手に集中力を失ってしまうケースが殆どである。
オフィスワーカーであれば、集中するためにはパソコンのブックマークを整理する必要があるかもしれない。
ついついAmazonを眺めてしまうのであればブックマークから削除しよう。Yahoo!ニュースが気になってしまうのなら同様にして削除。
デスクが散らかっていると気が散る場合がある。
集中の妨げになると感じるなら、視界に余計なものが入らないように整理しよう。
集中できる環境を構築することにより、自分で自分をコントロールするのである。
2. 先延ばし癖を克服するためのアイデア3選
全人類を悩ますものの一つに「先延ばし」が挙げられる。
先延ばしにはいいことなど何一つない。
だってそれはやらなければならない仕事なのである。
先延ばしにしておいたらやる必要がなくなってよかった!むしろ、やらなくてよかった!ラッキー!
ということは殆どない。
先延ばしにしてしまうことによって、定時間際にやるべき仕事が山ほど積み上がってしまい、結局終電コースとなってしまう。
どうせやるならさっさと片付けてしまおう。
2-1. やる気が出るのを待つ、は間違い。実際にやることによってやる気は出てくる
先延ばしの言い訳第一位は「今はやる気が出ない。やる気が出たら必ずやる」というものである。
なるほど、「やる気が出ないのなら仕方ないよね」と思ってしまいそうになるけれど、それは間違い。
やる気なんて待っていても、いつまで経っても出てこない。
やる気を待つのは間違い。
実は、やる気というものは、実際にやってみることによって出てくるものなのである。
実際に着手することによって、脳がその仕事モードに入り、終わらせるための見通しが立ち、それがやる気となるのである。
だから大切なことは、5分でもいいから、まずはその仕事に手をつけることなのである。
2-2. やりたくない仕事は重要な仕事であると自覚すること
先延ばしにしてしまう仕事とは、やりたくないと思っている仕事と同義である。
やりたくないというのは、心が抵抗していることに他ならない。
なぜ、抵抗してしまうのか。
それは、その仕事が重要な仕事であり、あなたを成長させてくれる仕事だからである。
重要な仕事であるだけに失敗を恐れてしまって手がつかなかったり、未知の仕事であったり、未知なだけに厄介なステップを踏まなければならなかったりする。
だから、やらなければと思っていても、ついつい足踏みしてしまうのだった。
でも今日からは、自分の中で先延ばしにしてしまっている仕事を見つけたら、「これは重要で、自分のためになる仕事なのだ」と考えるようにしてみよう。
少しはハードルが下がるかもしれない。
2-3. あえてスケジュールを立てないでみる
仕事の仕方には2種類ある。
ひとつは、計画を立てた上でやるべきことを可視化し、それに従って行う方法。
もう一つは、思い付いたことを思い付いた順に手当たり次第に片付けていく方法。
どちらでも正解はない。
わたくし個人的には計画をたてるのが好きだが、かつての私の上司たちの中にはどちらのタイプもいて、やり方は違うものの、どちらも非常に高い成果を挙げていた。
どちらを選ぶかは好みと性格によるものである。
今、もしあなたのスケジュールが目一杯で、見るのもうんざりしてしまうから仕事に手が付かないという状態であるなら、仕事のスケジュールのことは一旦忘れて、何も考えずに目に付いた仕事を目に付いた順に片付けてしまうというのも手である。
スケジュールにこなしきれない仕事が一杯で全然片付かないとなると、スケジュールのことを考えるだけで挫折感を味わってしまうことになる。
仕事で重要なことは、自発性である。
やるべき仕事に縛られてがんじがらめにされながら「早く終わらせろ」と脅迫されることほどつまらないものはない。
そんなスケジュールのことは忘れてしまうというのも、停滞を脱する一つの解決手段だ。
【厳選】先延ばし癖の心理とは?克服するための究極の3つの方法
3. 計画的に仕事を終らせるための完璧なTo Doリストの作り方3選
To Doリストの作成は、計画的な業務遂行への第一歩である。特に、自分は怠け者だと思う人にこそ作成をおすすめする。
To Doリスト・やることリストによって、本日やるべきことが可視化される。従って、一日の業務におけるペース配分が容易になるのである。
少なくとも、定時に帰ろうとしていたのに退勤1時間前になって「あれもこれもやってなかった」とバタバタ慌てることはなくなる。
To Doリストの作成にはコツが要る。
良いTo Doリストは仕事を捗らせるが、悪いTo Doリストはやる気を減退させる。
効果的なリストの作り方を教えよう。
3-1. 自発性を喚起するリストにすること
To Doリストがごちゃごちゃでは目も当てられない。自分のやるべきことを整理するためのリストだからである。
一目見てどれから手を付けたらいいのかわからないリストには何の意味もない。
同時に、見てもやる気が起きないようなリストも無意味。
例えば今、To Doリストが手元にあるけれど無用の長物になっているような場合は、そのリストはすぐさま捨ててしまって新しく作成することが望まれる。
リストは「これだけの仕事だから終わらせよう」という自発性を喚起するものであることが第一要件である。
そのためには、
・きちんと整理されていること
・一目見てわかりやすいこと
・やることが詰め込まれ過ぎていないこと
などが要請される。
各々「このリストの仕事は終わらせよう」と思えるTo Doリストを作成しよう。
3-2. 達成感のあるリストにすること
To Doリストにおける最大の快感は、終わった仕事をリストから横線で消すことである。
この快感を味わうためにリストを作成せよと言ってもいいくらいである。
人には、一つの仕事を終わらせることを快く感じる「完了バイアス」という機能が備わっている。
すなわち、それが達成感である。
本日の「やること」が全て横線で消し込まれたとき、最大の快感を得ることができるのだ。
達成感の多いリストを意図的に作成しよう。
それは例えば、
・今日のリストは今日だけで使用し、一日一日で達成感を得られるようにする。
・難しい仕事や長くかかる仕事は、小さなステップで達成感が得られるように細分化してリストに書くこと。
・後から舞い込んだ仕事を本日のTo Doリストに加えないこと。
などがポイントとして挙げられる。
3-3. 終わらせる自信のあるものだけをリストに加えること
とにかく今日のリストは今日終わらせることが肝心である。
そのためには、今日終わる分だけの仕事をリストアップすることが要請される。
そう、リストに今日終わりそうにない分量の仕事をそもそも加えないこと。
どうしても我々は未来をポジティブに捉えがちなようで、「これくらいは終わるだろう」と今日のリストに20も30も書き込んでしまう傾向にある。
断言しよう。根拠のない希望的観測で山ほど加えられた仕事は、絶対に終わらない。
せめて3つとか4つにするべきである。
その3つか4つの仕事が終わってしまったら、他の仕事を見つけてこなせばいいのである。
また、「後から舞い込んだ仕事」や「やることとは別のやりたい仕事」は、別にリストを作ってメモしておけば、今日のリストの妨げにならずに済む。
究極のToDoリストを作るために、絶対にやってはいけない3つのこと
4. 台所用タイマーを使えば仕事は捗る!実用的な3つの方法
我々は怠け者である。ついだらっとしてしまう。
そんな我々に台所用タイマーが有効な理由は、それが外部からの司令であると錯覚するからである。
自分でタイマーをセットしたにも関わらず、時を刻むタイマーに急かされるのである。まるで、上司や同僚に「このアラームが鳴る前に仕事を終わらせよ」と言われているかのように。
ともかく、自分で自分にプレッシャーを与えることで、仕事を集中して終わらせることができる。
社内でけたたましいアラームを鳴らすわけにはいかない場合、パソコンやスマートフォンのアプリケーションで代用しよう。
4-1. 手強い仕事はまず5分間だけやってみる
どうしてもやる気が出ない仕事は、アラームを5分にセットして取り掛かってみよう。
まずは始めることが肝心である。
たった5分間だけなのだから、何も恐れることはない。
往々にして我々は長くかかかりそうな仕事を敬遠してしまう傾向にある。「今始めたら、延々とやり続ける羽目になってしまうのではないか」と。
長くかかる仕事だからと言って、ずっとそれに集中していなければならないわけではない。
かといって、いつまでも始めないのではいつまでも終わらない。
だから、まずは5分間だけやってみよう。たった5分である。かなりハードルは低いはずだ。
4-2. 時間に余裕がある場合は25分間のインターバル
もしまとまった時間があって集中して仕事に取り組みたい場合、タイマーを25分にセットして取り組んでみよう。
25分が経ったら、5分の休憩を挟んで、また25分間集中する。
それの繰り返し。
長い時間を25分毎に区切ることで間延びせずに仕事に集中しやすくなる上、25分というのは集中力が途切れないで仕事に取り組めるベストな時間なのである。
集中している25分間はあっという間だ。
数時間単位のまとまった時間を有意義に集中したい場合、有効な戦略である。
引っ越しの荷造りの際の時間管理などにも使えそうだ。
4-3. 単純作業を集中してこなすには、ごく短時間を目標にする
単純作業の繰り返しは、だらっとしがちである。
難しい仕事ではないだけに退屈を持て余してしまうのだ。
そんな時には、タイマーを短時間にセットしてテキパキとこなすのが良い方法である。
基準としては、通常かかると思われる時間の25%を目標にするといいだろう。
だらっとやって1時間かかるところを、テキパキと15分で終わらすのだ。
【仕事術】タイマーを使って仕事を劇的・効率的に片付けるアイデア3選
5. ホフスタッターの法則。仕事は必ず遅れる。それでも期日内に終わらせるコツ2選
ダグラス・ホフスタッターが提唱した「ホフスタッターの法則」は誠に興味深い。
計画中のどんな仕事も完成には予測以上の時間がかかる――たとえ、このホフスタッターの法則を計算に入れても。
全ての仕事は計画よりも遅れる運命にあるというのだ。遅れることを見越して計画を立てても、絶対に遅れる。
日本人は真面目だから納期はきちんと守る傾向にあるが、それでも待望のものが発売延期になったりする例は枚挙に暇がない。
我々の普段の仕事でも、計画が守られた例のどれほど少ないことか。殆どの場合は遅れて進行するのであり、自分で立案した計画も守れない人が多いこと(私を含む)。
では、どうすれば計画を計画通りにこなすことができるだろうか。
5-1. 「感覚」で計画を立ててみる
一般に、計画は論理で組み立てるものだが、実はそれには限界がある。
どうしても想定外な事態が起こったりするからである。我々はロボットではないから、どうしても捗らない日というのもある。
であれば、論理よりも感覚重視で立案してみるというのも一つの手ではないだろうか。
論理としては一週間で終わるはずだが、いや待てよ。前にも同じようなプロジェクトが二週間かかったじゃないか――。
というように、理詰めでガチガチに立案されたものよりも、むしろ現実に近い計画が出来上がるかもしれない。
5-2. 計画を立てない
計画を立てないで何事もうまくいくわけないじゃないか。
わかります。
私も計画を立てるのが好きであり、大きなプロジェクトは計画なしでは不安である。
大人数を巻き込むようなプロジェクトではさすがに計画なしというわけにはいかないが、個人的なことや少人数であれば可能かもしれない。
計画をあえて立てないで、実行しながら軌道修正していくという方法である。
やってみないとわからないことは、計画を立てるよりもまずはやってみたほうがうまくいくかもしれない。
加え、そもそもの計画が間違っていた場合、計画に固執することは間違った完成にたどり着く恐れもある。
計画を立てずに、実際に手を動かしながら進めていくという方法もあるのだと覚えておこう。
計画が必ず遅れるのはなぜか。ホフスタッターの法則とそれを回避するアイデア2選
6. スキマ時間を有効活用するためのアイデア4選
「時間がない」と感じるのは、つまりは「まとまった時間がない」という理由による。
スケジュールが過密で数時間単位のまとまった自由な時間がなかったり、集中できる環境になかったりするためである。
従って、皆、少しの時間でできるスマホゲームを暇つぶしにプレイするのである。
そう、時間がないわけではないのだ。スマホのゲームをする時間はある。
現代は時間が細切れになっている。のんびりとした自由でまとまった時間はなかなか取れない。
であれば、その細分化された自由時間を有効活用するしかないのである。
スマホゲームが悪いと言っているわけではない。私もよくやる。
ただ、暇つぶしにスマホゲームをする時間があるということは、他のこともする時間があると考えてみてはどうだろうか。
6-1. まとまった時間でやらなければならない仕事はない
大きなプロジェクトや時間がかかりそうな仕事、長考しなければならない仕事は、時間のあるときにゆっくりやりたいと思うだろう。
だけど我々の殆どの時間は細分化されてしまっている。
ゆっくりした時間なんて訪れない可能性が高いと考えたほうが良さそうである。
6-1-1. 仕事を細分化すること
難しそうな仕事も小さなステップにわけることによって、わずかな時間の積み重ねの中でも着実にこなしていくこと。
大きなまとまりで考えるよりも、仕事も細分化してしまったほうが手を付けやすいのだ。
6-1-2. 大きな仕事でも時間をかける必要はない
あるいは、大きな仕事だから時間をかけなくてはならない、という既成概念を覆すことである。
過去に似たような事例があったなら、それを流用するもよし。
あまり考えないで大雑把に仕上げるもよし。
それなりの出来で早く終わらせるに越したことはない。
6-2. 同じ種類の仕事はまとめてやってしまう
仕事を切り替えている時間というのが最も無駄であり、浪費されている時間であることがわかっている。
従って、メールなら時間を決めて一度にまとめて返信したほうが効率的である。
デスクの一箇所が気になって片付けるなら、ついでに机全体を綺麗にしたほうがいいかもしれない。
仕事の切り替えの時間が一番無駄、ということを念頭に置いて仕事をこなしてみよう。
6-3. スキマ時間に適した仕事をする
スキマ時間に適した仕事の三箇条というのがある。
a. どこへでも持っていけること
b. 気の散る環境下でも集中してできること
c. 数秒の作業であっても結果を残せること
スマホゲームをスキマ時間についついプレイしてしまうのは、これら条件を満たしているからに他ならない。
10分程度でも充実感を得られる。
スキマ時間に何をすればいいかわからない人は、上記三箇条を意識してみるとヒントが得られるかもしれない。
ちなみに私は、10分程度のスキマ時間にブログ執筆をよくする。
やる前には、文章というものは腰を据えて書かなければならないと思い込んでいたものの、実際やってみるとスキマ時間でも充分に書き上げることができることに驚いた。
とりあえずはやってみることが大事だ。
6-4. あえて何もしない時間にする
常に何かをしなければならないわけではない。
「何かしなければと思いつつも結局何もできなかった」という時間は疲れるだけであり、挫折感も味わうこととなる。
であれば、意識的に何もしないという時間にしてみるのも有意義であると私は考える。
休息に充てることで、次の仕事に集中して取り組む活力にもなるだろう。
7. 仕事をランク付けしても意味ない。だったらどんどん減らそう
重要度によるABC格付けシステムの欠陥
仕事を重要度によってABCランクを付けていく、という手法がある。
最重要項目はAであり、それなりに重要なことはB、あまり重要ではない仕事はC、というように。
この手法はなかなかメジャーな考え方で、実際に取り入れてみている人もいるかもしれない。
ただ、それが本当に仕事の効率化に繋がるかどうかとは別問題である。
「A=最重要な仕事」については直ちに片付けなければならないということはわかる。誰もが仕分け後にはAから取り掛かるだろう。
だったら、それ以外をBやCと格付けすることには、どれほどの意味があるのだろうか。
この重要度による格付けシステムは、1974年にアラン・ラーキンなる人物が出版した著書によって爆発的に広まり、支持されたものである。
ただ、この手法は1974年発案ということもあり、情報化社会と言われる現代には通用しない方法なのではないかと私は考えている。
ABC格付けシステムは少ない情報の中で「あれもやりたい・これもやりたい」を実現させるための方法だからである。
現代は誰もが無意識にマルチタスクを背負わされている
だけど、現代は情報が溢れているために、大した情熱を持っていない人でもやりたいことが山のようにある。
「あれもやりたい・これもやりたい」を全て実現することは不可能であるばかりか、そういった姿勢では結局何もできないまま時間だけが過ぎてしまう恐れが大きい。
会社も従業員に「あれもやらせたい・これもやってもらいたい」と思っているから、キャパシティ以上の業務を押し付けることとなる。
誰もが無意識にマルチタスクを抱えたまま・抱えされられたまま、結局はマルチタスクそれ自体が非効率の元凶となっているのが現代の特徴である。
そういった中にあって求められるのは意識的な「シングルタスク」の姿勢だ。
「あれも・これも」ではなく、「これだけ」という姿勢である。
そう、求められているのは「やるべきことを厳選すること・減らすこと」である。
仕事をABCランクで格付けしても、次から次へと仕事が押し寄せてくるためにAランクの仕事さえままならない。
そうなるとB・Cに格付けした仕事なんてできるわけないのである。
マルチタスクでは全てが中途半端になってしまって、結局は何も達成できない。
やるべきことを厳選して集中して取り組もう
格付けではなく、取捨選択をしよう。
やるべきことを自分の意志で厳選しよう。
AAAランクの仕事だけを集中して取り組んで、他のものは思い切って切り捨てよう。
そうすることによって、効率的に仕事がどんどん片付いていく。
集中して効率的に仕事が片付けば、颯爽と定時に帰ることができるというわけである。
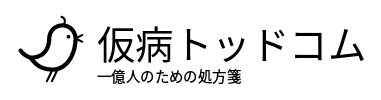

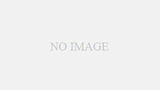
コメント