私がかつて勤めていた会社で、新規事業を始めることとなった。社員数10名程度の零細企業であり、社長のワンマン経営である。
その事業というのは、寂れた地方百貨店への出店であった。
誰がどう考えても成功するとは思えなかった。
だけど、どういう打算があったのかわからないが社長は極めてポジティブであり、店を設えるための莫大な工事費と割高な出店料を支出して、開店させた。
結果、収支は散々であった。
1ヶ月たりとも黒字になったことさえなかった。毎日が大幅な赤字であり、人件費さえ捻出できない。出店資金の回収どころの話ではなかった。
営業すればするほど負債が増えていくのである。
要因は様々である。
そもそもの出店計画が間違っていたこと。人員教育がなっていなかったこと(店長と呼ばれる人物は電卓の使い方さえわからないような者であった)。
だけど、一番の問題なのは、会社の経営を傾かせるほどの大赤字店舗を2年間も営業し続けさせたことである。
毎日が大赤字なのであり、改善の見込みがないのは開店3ヶ月後には誰が見ても明らかだった。
にも関わらず、社長は閉店という英断を下すまでに2年もかかった。
なぜか。
私が考えるに、一貫性にこだわるあまり、正常な判断が下せなかったのである。
一貫性の原理とは?
これは、心理学では「一貫性の原理」と呼ばれている。
人は、自分の行動に一貫性を保ちたいと考えている。
つまらないと思ってもやめられない
例えば、あるマンガを好きで読んでいたが、連載途中から面白くないなと感じ始めても、ここまで読んできたのだからと思ってやめることができない。
コミックスを買っていたとすれば、1巻から集めていたのだからやめるわけにはいかないと集め続けてしまうこと。
コレクター気質の人は、一貫性の原理に突き動かされて収集しているとも言える。
試食を勧められると買ってしまう
スーパーでの試食も、我々消費者の一貫性の原理を刺激するものである。
試食を勧められて食べてしまう
↓
「どう? 美味しいでしょう」
↓
「はい、美味しいですね」
↓
一貫性の原理:食べてしまったし、美味しいと言ってしまった。買わなきゃ悪いかな。
Amazon「こちらの商品もおすすめです」
私はAmazonで本を買うことが多いのだが、欲しいものをカートに入れると、「こちらも買われています」と他の似たような書籍がおすすめされてきて、ついつい買ってしまうのである。そういう経験はないだろうか?
これも、一貫性の原理で説明ができる。今興味のあるものについてより一層の見識を深めなくてはならないとの心理が働くことによるものだ。
一貫性の原理は、セールスマンの最も基本的な戦略でもある。
一貫性を堅守することの何が問題か
趣味の範囲で好きな物をコレクションすること、試食で食べてみて美味しかったからと夕飯の一品に加えることは、何の問題もない。
それは人生を豊かにしさえするかもしれない。
人が自分の行動に一貫性を保ちたいと考えることには、大きく分けて二つの理由があると言われている。
1. 言動に一貫性のある人は社会的に高く評価される傾向にあるから
2. 複雑で様々な要因の絡み合う世の中において、意志決定プロセスを簡素化するため
一貫性それ自体は悪いことではなく、むしろいいことであるとも言える。
コロコロと意見や行動の変わる人よりも、言動が一貫している人のほうが信頼がおけるような気がするのは自明である。
何かを判断する時、頭の中の一貫性が情報を自動的に整理してくれることで、決断がしやすくなること。また、その判断に関わる不安や心配を和らげてくれる効果もある。
では、一貫性の何が問題か。
それは、人は一貫性を保つために、合理的でない、常軌を逸した行動を取ることさえあるということである。
「一貫性を保つべきだ」というくだらない考えが邪魔をして、その時その時の最善の行動を選ぶことができないことにもなり得るのだ。
さよなら優柔不断。理性と直感、両方を上手に使って正しく決断するための4つの方法
一貫性は不合理であることもある
自分が賭けた馬が勝つと信じてしまうこと
複数の研究結果によると、競馬で一頭の馬に賭けた時、その馬の勝利を信じる気持ちは、賭ける前よりも賭けた後のほうが強くなるという。
これは大変に不合理なことであると私は思う。
賭ける前と賭けた後で、その馬の状態は何も変わっていない。レースに関する新たな情報がもたらされたわけではない。
つまり、その馬が勝てる見込みや要因が増えたわけではないし、勝つ可能性があがったわけでもない。何も変わっていない。
にも関わらず、「自分がその馬に賭けた」というその主観的な事実だけで、勝利を信じる気持ちが強くなってしまった。
「自分が賭けた馬である → だから勝つはずだ」という根拠のない一貫性のためである。
これが合理的な判断と言えるだろうか。自分の脳に自分自身が騙されているとしか思えないのだった。
「結婚なんてしたくない」友人
また、私の友人に「結婚なんてしたくない」と言いながら交際二年で結婚し、「結婚なんてしなきゃ良かった」と悪態をつき続けている者がいる。
じゃあなんで結婚したんだろうか、と単純に思ってしまうわけだが、これも一貫性のせいだ。
自分から恋に落ちて、情熱的な愛の告白をして交際が始まったわけだが、その最初の情熱から自分が一貫していることを示さなければならないと心に感じているのであろう。
だから、悪態をつきながら結婚式を挙げ、悪態をつきながら結婚生活に甘んじている。
まだ子供はいないようであるが、私の予測では、一貫性を保つために嫌々ながら子育てをし、絶対に買いたくないと言っている家を一貫性のために建て、「結婚なんてしなきゃよかった」と言いながら一貫性を証明するために寄り添って最期のときを迎えるのである。
一貫性を保とうとするあまりに合理的な判断ができずに、悲惨で退屈な結婚生活に甘んじてしまったと言えよう。
なぜ赤字の事業を切り捨てられないのか
ここまで来たらもうおわかりであろう。
冒頭で紹介した、赤字事業を2年間に渡って切り捨てられなかった社長の話である。
特にその赤字事業を継続し続けなければならない特別の理由もなかったようであり、早々と撤退しなかったことは全く合理的でない。
にも関わらず、2年間も巨額赤字を累積させた挙句、会社の経営が本格的に傾き始めた頃、ようやく撤退の英断をした。
つまりは、一貫性を保ちたかった、ただそれだけの話である。
自分の独断によって鳴り物入りで始めたその事業について、撤退する勇気がなかった。
プライドが邪魔をした。
売れると思って始めたからには、売れることを示したかった。
待っていれば売れる日が来ると思っていたが、結局は売れなかった。
ただそれだけ。
我が社の経営を無慈悲にも傾かせた諸悪の根源。
それが一貫性である。
苦労話をする上司や社長は無能。無能な上司にならないためのたった一つの方法
一貫性に惑わされない正しい判断のための2つの方法
一貫性にこだわることは、自分の選択が間違っていなかったと思うための防御の戦略に他ならない。
間違っていたことを認めないために赤字店舗の撤退を限りなく先延ばしにした。
赤字店舗はさっさと撤退したほうが賢明であり、合理的なのである。
早くに手を打っていれば会社の借金もここまで膨らむことはなかった。
合理的な判断のために、次の二つのことを覚えておこう
一貫性を保とうとしているだけなのではないかと常に疑問を持つ
人は自分の判断は常に正しいと思い込む傾向にある。
なぜなら、間違いなく自分の意志で決断しているという実感があるからである。
だけど、常に正しくて、合理的は判断をしているか、ということとは別問題なのである。
我々の意識の裏には、今回紹介した一貫性の原理のような、全く不合理な判断を我々にそそのかすものもある。
だから、常に自分の意識さえも疑うということが正常な判断のためには重要になってくる。
「なぜ赤字なのに撤退できないのか。そうか、私は一貫性を保とうとしているだけなのかもしれない」と気づくことができれば、もう少し早めに英断を下せたかもしれない。
得られた情報を平等に扱う
我々は、情報を頭の中で偏らせて処理している。
これは重要なこと。これは不要。これは重要だけど知りたくない。など。
重要だけど知りたくない情報を放置した結果の代表例が、雪だるま式に膨らむ借金である。
普通に考えれば借金が増えることは良くないことなのだが、脳がそのように解釈してくれなかったがために、多重債務となってしまうのだった。
一貫性の原理において、重要な情報処理は時系列に注意することである。
ここに出店すれば売れると意気込んで投資したが、全く売れなかった。投資してしまった手前、撤退に踏ん切りが付かない。
そのような状況であれば、後から得られた情報を重要視してみるのである。
つまり、「全く売れない」とわかっていたら、出店しただろうかと考えるのだ。答えは絶対に「ノー」だ。
であれば、出店してしまった手前であっても、速やかに撤退することが賢明であると判断できるだろう。
後から得られた情報を予め知っていたとしたら、どのように判断するだろうか、と考えることは、凝り固まった我々の考え方に新たな視点を授けてくれることが多いと私は感じている。
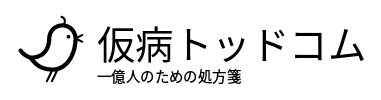

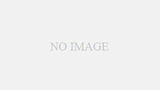
コメント